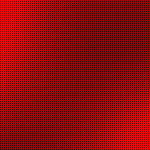M&Aによる従業員の承継のポイント①
M&Aをすると従業員はどうなるか
M&Aによって経営者が交代するとしても、売り手に勤務していた従業員は引き続き勤務し続けることになるのでしょうか。M&Aの後も企業が事業を進めるためにもこれまでどおり従業員に勤務してもらう必要があることが多いと考えられます。他方で、M&Aに伴う事業の縮小のために人員整理を行ったり、いわゆる問題社員について、M&Aをきっかけに退職してもらいたいと考えたりすることもありえます。
そこで、今回は、M&Aに伴う従業員の雇用関係について解説します。
〇 株式譲渡によるM&Aの場合
株式譲渡によるM&Aの場合は、株主構成が変わるだけなので、従業員の雇用関係に特段の変化が生じるわけではありません。では、M&Aをきっかけに従業員を解雇することはできるのでしょうか。結論としては、単にM&Aにより経営者が交代することは解雇の合理的な理由になりませんので、解雇権の濫用(労働契約法第16条)として当該解雇は無効となります。
では、M&Aに伴い、工場などの事業所を閉鎖するため従業員を解雇する場合はどうでしょうか。この場合は、いわゆる整理解雇にあたりますので、解雇が可能かどうかは、いわゆる整理解雇の4要件(東洋酸素事件:東京高判昭和54年10月29日労判330号71頁)を満たすかどうかを検討することになります。
| 【整理解雇の4要件】
① 人員削減の必要性 人員削減措置の実施が不況、経営不振などによる企業経営上の十分な必要性に基づいていること ② 解雇回避の努力 配置転換、希望退職者の募集など他の手段によって解雇回避のために努力したこと ③ 人選の合理性 整理解雇の対象者を決める基準が客観的、合理的で、その運用も公正であること ④ 解雇手続の妥当性 労働組合または労働者に対して、解雇の必要性とその時期、規模・方法について納得を得るために説明を行うこと (出典:厚生労働省ウェブサイト) |
事業譲渡によるM&Aの場合
事業譲渡とは、事業の全部または一部を取引行為として第三者に譲渡する行為をいいます。ここにいう「事業」とは、「一定の目的のために組織化され、有機的一体として機能する財産」をいいます(最判昭和40年9月22日民集19巻6号1600頁)。飲食チェーンがひとつのブランドを売却する際に、店舗、セントラルキッチン、システム一式を譲渡第三者に売却するという事例をイメージするとわかりやすいかもしれません。
事業譲渡は事業を譲渡する会社(以下「譲渡会社」といいます。M&Aにおける売り手を指します。)とこれを譲り受ける会社(以下「譲受会社」といいます。M&Aにおける買い手を指します。)との契約によって行われます。したがって、譲渡会社の雇用関係を譲受会社の雇用関係に承継させるためには、当該契約に雇用関係を承継させる旨を規定することがまず必要になってきます。さらに、事業譲渡により雇用関係が譲渡会社から譲受会社に承継するためには、各従業員の承諾が必要とされています(民法第625条)。いわば、事業譲渡の場合は、譲渡会社の従業員には譲受会社への転籍の拒否権が与えられているといっても過言ではありません。
したがって、譲渡会社は、事業譲渡によって移籍をさせようとする従業員から承諾を得るためには、事業譲渡に関する全体の状況や譲受会社等の概要及び労働条件等を丁寧に説明し、当該従業員の真意による承諾を得られるようにする必要があります。
また、譲渡会社に労働組合がある場合は、個々の従業員への説明に先立ち、労働組合への協議を行い、理解と協力を得るよう努めるべきです。事業譲渡による従業員の転籍は、労働条件に関する重要な事項ですので、労働組合は交渉権限を有しています(労働組合法第6条)。したがって、労働組合から事業譲渡による従業員の転籍について団体交渉を求められた場合、これを拒否すると不当労働行為となりますので(労働組合法第7条第1項第2号)、注意が必要です。(以上について、詳しくは、「事業譲渡又は合併を行うに当たって会社等が留意すべき事項に関する指針」(厚生労働省告示第318号)をご参照ください。)
事業譲渡によるM&Aでは買い手は転籍する従業員を選ぶことができる?
先ほども述べたように、事業譲渡により従業員を譲渡会社から譲受会社に転籍させるためには、譲渡会社、譲受会社及び当該従業員の3者の合意が必要となります。
逆に言えば、譲渡会社と譲受会社とが合意しなければ特定の従業員は譲渡の対象から外されることとなります。そうすると、買い手である譲受会社としては、譲渡会社からの転籍を望まない従業員について、事業譲渡の対象から外すことも理論的には可能ということになります。
ただし、譲受会社が、譲り受けた主要な資産や事業所の所在地や電話番号ロゴマークを引き続き使用していることや事業譲渡の対象とならなかった従業員以外の全従業員を雇用していることなどから、すべての従業員を譲渡の対象とする事業譲渡がなされたと推認されると判断した裁判例もあります(タジマヤ事件:大阪地判平成11年12月8日労働判例777号25頁)。また、法人格否認の法理を用いて事業譲渡の対象から外れた従業員を救済した裁判例もあります(日進工機事件:奈良地判平成11年1月11日労判753号15頁など)。
したがって、恣意的に従業員を事業譲渡の対象から外したとしても、訴訟などを通じ、結局譲受会社に雇用関係が承継されていると認定されてしまうリスクがあるということを認識しておいたほうかよいのではないかと考えます。
次回の予告
次回は、合併や会社分割によるM&Aの際の雇用関係の承継について取り上げますのでご期待ください。